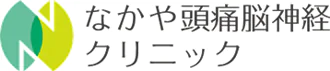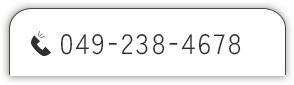頭痛の種類と特徴
片頭痛
 片頭痛は脈打つような痛みが頭の片側に現れて、頭痛と共に音や光、においに対して敏感になったり吐き気を伴ったりすることがあります。
片頭痛は脈打つような痛みが頭の片側に現れて、頭痛と共に音や光、においに対して敏感になったり吐き気を伴ったりすることがあります。
女性に多く見られ、男性に比べて約4倍の発症率が報告されています。カフェイン、アルコール摂取や日常的なストレスなどが頭痛を引き起こす誘因となることがあります。
緊張型頭痛
緊張型頭痛は肩や首周りの筋肉の緊張が積み重なることによって起こる頭痛です。痛みは締め付け感や頭重感が主体で日常生活における最も一般的な頭痛です。患者数は約2000万人とされています。デスクワークやPC作業など同じ姿勢での仕事を長時間行う人に多く見られます。
群発頭痛
 群発頭痛は、片側の目の奥をアイスピックで刺されるような激しい頭痛で、鼻水や涙、目の充血を伴うことがあります。一般的な鎮痛薬では効果がなく、毎日同じ時間帯に発生しやすいといった特徴があります。痛みは15分~3時間程度続いた後、突然何もなかったかのように治まります。多くの場合では1〜2か月程度痛みの起こる日が続きます。
群発頭痛は、片側の目の奥をアイスピックで刺されるような激しい頭痛で、鼻水や涙、目の充血を伴うことがあります。一般的な鎮痛薬では効果がなく、毎日同じ時間帯に発生しやすいといった特徴があります。痛みは15分~3時間程度続いた後、突然何もなかったかのように治まります。多くの場合では1〜2か月程度痛みの起こる日が続きます。
薬物乱用頭痛
薬物乱用頭痛とは一次性頭痛のための頭痛薬を3か月以上に渡り定期的に内服しており、月に10日または15日以上起こる頭痛と定義されています。特に入手しやすい市販の鎮痛薬による内服の乱用が原因で発生することが多いとされています。
頭痛薬が効かない理由と対処法
薬を服用するタイミング
 頭痛が始まった際にすぐに薬を服用しないと、痛みの原因物質が体内で増加し、鎮痛薬の効果が十分に発揮されないことがあります。そのため、鎮痛薬は痛みを感じ始めたタイミングで服用することが重要です。
頭痛が始まった際にすぐに薬を服用しないと、痛みの原因物質が体内で増加し、鎮痛薬の効果が十分に発揮されないことがあります。そのため、鎮痛薬は痛みを感じ始めたタイミングで服用することが重要です。
頭痛の原因にあっていない
上記にあるように頭痛の種類はいくつかあるため、原因となる頭痛にあった薬の内服をしなければ効果が得られないことがあります。特に片頭痛の発作時には市販薬が有効ではないことが多く、寝てやり過ごすことになったりします。
薬自体が身体に合わない可能性
頭痛薬にはさまざまな種類があり、薬の効果の強さや作用時間が個人によって異なるため、適切な薬を選ぶことが重要です。
- 現在使用している鎮痛薬を服用しても効果がない場合は、薬が身体に合っていない可能性があります。
- 頭痛が頻繁に続き、普段の薬でも改善しない場合は、重大な疾患が潜んでいることも考えられるため、一度服用を中止し、脳神経外科を受診することをおすすめします。
頭痛薬の種類と注意点
非ピリン系鎮痛剤(NSAIDs)
非ピリン系鎮痛剤(NSAIDs)には、イブプロフェンやロキソプロフェンなどがあります。
痛みの原因物質であるプロスタグランジンの生成を抑えることで鎮痛効果を発揮します。そのため、痛みを感じたらできるだけ早めに服用するようにしましょう。
注意点
痛みの原因となるプロスタグランジンは、胃の粘膜を保護する働きも持つため、胃が弱い方が非ピリン系鎮痛剤を服用する際には注意が必要です。胃への負担を軽減するために、胃の粘膜を保護する成分を含んだ鎮痛剤もあります。胃への影響が気になる場合は、食後に服用する、胃薬と併用する、医師や薬剤師に相談するなどの対策をとるとよいでしょう。
ピリン系鎮痛剤
ピリン系鎮痛剤は、非ピリン系鎮痛剤よりも高い鎮痛効果が期待できる鎮痛薬です。現在、市販薬として販売されているピリン系鎮痛剤にはイソプロピルアンチピリンがあります。
注意点
ピリン系鎮痛剤は強力な鎮痛作用を持つ一方で、非ピリン系鎮痛剤と比べてアレルギー反応を引き起こすリスクが高いため、使用には注意が必要です。過去に薬剤アレルギーを経験したことがある方や、アレルギー体質の方は、服用前に医師や薬剤師に相談することをおすすめします。
漢方薬
漢方薬には鎮痛剤のイメージがあまりないかもしれませんが、頭痛の種類に応じて効果が期待できるものがあります。症状に合わせて選ぶことで、自然な形で頭痛を緩和することが可能です。
また、漢方薬は、一般的な鎮痛剤(NSAIDsなど)と併用できるものもあり、症状や体質に合わせて組み合わせることで、より効果的な頭痛管理が可能です。漢方の使用を検討する場合は、医師や薬剤師に相談しながら適切に活用しましょう。
例として、
- 緊張型頭痛には「葛根湯(かっこんとう)」
葛根湯には筋肉の緊張を和らげる作用があり、肩こりや首のこりが原因となる緊張型頭痛に効果が期待できます。 - 片頭痛には「呉茱萸湯(ごしゅゆとう)」
呉茱萸湯は、血流を改善し、ズキズキと脈打つような痛みを和らげる作用があるため、片頭痛に効果があるとされています。 - 高血圧傾向の頭痛には「釣藤散(ちょうとうさん)」
釣藤散は、血圧が高めで、めまいを伴う頭痛に効果があるとされており、高血圧による頭痛の改善が期待できます。
市販の頭痛薬の選び方
頭痛薬や解熱鎮痛剤は、頭痛の種類や他の症状、体質に合わせて適切なものを選ぶことが重要です。特に以下の点に注意しましょう。
- 喘息をお持ちの方
一部の頭痛薬には、喘息を誘発する可能性のある成分が含まれているものがあります。喘息の持病がある方は、市販薬を購入する際に必ず薬剤師に相談し、適切な薬を選びましょう。 - 過剰な服用
頭痛薬を1ヵ月に10日以上服用すると、薬物乱用性頭痛を引き起こす可能性があります。頭痛が慢性的に続く場合は、自己判断で薬を飲み続けるのではなく、早めに医師に相談しましょう。
風邪の際に発熱を伴う頭痛
頭痛薬には鎮痛作用だけでなく、解熱作用もあるため、風邪や発熱を伴う頭痛にも有効です。特に、風邪の際は片頭痛が悪化することもあるため、症状に応じて適切な薬を選ぶことが大切です。
また、頭痛薬は歯痛、筋肉痛、生理痛などにも効果があるため、必要に応じて使用できます。
胃への負担が気になる場合
一般的な頭痛薬や解熱鎮痛剤には、胃の粘膜を刺激し、胃が荒れる副作用があります。そのため、胃が弱い方は、できるだけ胃に優しい薬を選ぶようにしましょう。
- アセトアミノフェン製剤(例:タイレノール):胃に負担が少なく、空腹時でも服用可能
- ロキソニンSクイック:胃を保護する成分が配合されているため、比較的胃への影響が少ない
強い頭痛がある場合
強い痛みを和らげるためには、即効性と高い鎮痛効果を持つピリン系鎮痛剤の選択が効果的です。市販薬として許可されているピリン系鎮痛剤には、イソプロピルアンチピリンが含まれています。
代表的な薬として、「セデス・ハイ」があります。セデス・ハイには、イソプロピルアンチピリンに加え、カフェインやアセトアミノフェンなどの頭痛を抑える複数の有効成分が配合されております。
ピリン系鎮痛剤の注意点
ピリン系鎮痛剤はアレルギーを引き起こすリスクがあるため、服用には注意が必要です。特に、過去にピリン系鎮痛剤でアレルギー反応を起こしたことがある人は使用できません。
効果が不十分な場合は医療機関へ
市販の鎮痛剤を服用しても頭痛の改善が見られない場合には頭の中に病気が潜んでいる場合や市販薬の効きづらい片頭痛の発作である場合などがあります。強い頭痛が続いて市販薬で改善しない場合には医療機関を受診して医師に相談することをお勧めします。
病院を受診すべき頭痛
頭痛の中には、脳の疾患が原因で起こる場合があり適切な診断と治療が必要な時があります。特に、頭痛薬を服用しても改善しない場合には脳に異常がある可能性も考えられるために注意が必要です。
以下の症状がある場合は、早めに脳神経外科を受診しましょう。
- 頭痛薬が効かない
- 原因不明の頭痛の症状ある
- 頭痛を繰り返す
- 生活に支障をきたす頭痛がある
- めまいやふらつき、痺れなどの症状を伴う頭痛がある
- 今までで感じたことがないほど強い頭痛がある
- 滅多に頭痛にならないが、50歳以降で初めて感じるようになった頭痛がある