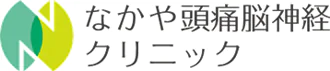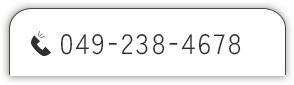- 頭をぶつけると危ない場所とは?
- 頭をぶつけた後に現れる注意すべき症状
- 子どもが頭をぶつけた場合の注意点
- 頭部外傷とは
- 頭部外傷による病気
- スポーツによる頭部外傷
- 高齢者の頭部外傷
- 労災で受診される方へ
頭をぶつけると
危ない場所とは?
 立ちあがろうとした際に何かで頭を打った、階段から落ちた、足元がふらついて転倒した、交通事故で頭を打撲した、スポーツ中の接触プレーで頭をぶつけたなど、日々の生活で誰もが一度は「頭をぶつけた」という経験があるかと思われます。
立ちあがろうとした際に何かで頭を打った、階段から落ちた、足元がふらついて転倒した、交通事故で頭を打撲した、スポーツ中の接触プレーで頭をぶつけたなど、日々の生活で誰もが一度は「頭をぶつけた」という経験があるかと思われます。
頭の打撲に最も影響を与えるものは衝撃です。交通事故や転落、意識を失って転倒して頭をぶつけた場合などは大きな衝撃を受けやすいです。
そのため、頭にはぶつけると危ない特定の部位はありません。しかし、ぶつけた頭の部位と受けた衝撃によって、注意すべき危険な症状が現れることがあります。
頭をぶつけた後に現れる
注意すべき症状
以下のような症状が見られた場合、速やかに医師の診察を受けましょう。
- 頭痛が続く
- 何度も嘔吐する
- 痙攣が生じる
- 頭をぶつけた前後の記憶がない
衝撃による
頭の場所ごとの影響
側頭部
側頭部は頭蓋骨が薄く、骨折が起こりやすい部位です。
側頭部の頭蓋骨に骨折が起こると、耳からの出血や脳脊髄液という透明な液体が漏れてくることがあります。また、頭蓋骨の内側には血管が通っており、衝撃によってこの血管が切れてしますと、脳を圧迫するような出血を起こすことがあります。
目の周囲
前方からの殴打や野球のボールがぶつかったりすると眼の周りの骨(眼窩)に骨折が起こります。眼球の動きに障害が起こり、物が二重に見える(複視)症状が現れることがあります。
後頭部
後方に転倒して後頭部を強打すると、首の痛みや肩こりなど、むち打ち症(医学用語では外傷性頚部症候群、頚椎捻挫)を生じることがあります。
子どもが頭をぶつけた場合の
注意点
小さなお子様は、自分の症状をうまく伝えることが難しいことがあります。そのため、以下のような、普段と違う様子が見られた場合は、医師の診断を受けましょう
- 機嫌が悪く、食欲がない
- 何度も嘔吐する
- 痙攣(ひきつけ)が起きる
頭部外傷とは
頭部外傷とは、外からの衝撃によって頭の皮膚、頭蓋骨、または頭蓋内の脳が損傷を受けることを指します。症状の程度はさまざまで、軽度なたんこぶ(皮下血腫)から、頭蓋骨骨折や脳挫傷に至るまで幅広くなります。
重症の頭部外傷の原因として最も多いのは交通事故です。しかし近年では高齢者の家庭内での転倒や転落事故も増加しております。
頭部外傷後の注意点
 頭を打った後に、頭痛と嘔吐の症状に引き続いて、意識障害や手足の麻痺といった強い症状が現れることがあります。これらの症状が出た場合には脳挫傷や脳出血といった脳内に損傷が生じている可能性が考えられるので、早期に医療機関への受診が必要です。
頭を打った後に、頭痛と嘔吐の症状に引き続いて、意識障害や手足の麻痺といった強い症状が現れることがあります。これらの症状が出た場合には脳挫傷や脳出血といった脳内に損傷が生じている可能性が考えられるので、早期に医療機関への受診が必要です。
また、徐々に症状が出現することがあることから、頭部を打撲した直後の6時間は症状の出現や変化に注意して観察を行うことが重要です。念のために頭部を打撲した後の24時間は通常とは異なる様子がないかに注意を払ってください。
もし以下のような症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診してください。
- 頭痛が徐々に強くなる
- 吐き気・嘔吐
- 意識がもうろうとする・放っておくとすぐに眠ってしまい、呼びかけてもなかなか目覚めない
- 物が二重に見える・はっきり見えずぼやける
- 手足が動かしにくい
頭部外傷による病気
脳震盪
脳振盪(のうしんとう)とは、頭部への衝撃によって一時的に脳の機能が乱れる状態になって一過性の意識障害や記憶障害が認められることを指します。基本的には、脳実質に損傷(器質的損傷)は生じていません。
以下のような症状がみられる場合は、脳振盪の可能性が高いと考えられます。
- 短時間の意識消失
- 一過性の健忘(頭をぶつけた前後の記憶がない)
- 頭痛
- めまい
- 気分の不調(吐き気、倦怠感など)
- 睡眠障害
- 音や光に過敏になる
など
脳振盪の症状は、多くの場合2週間以内で自然に回復しますが、小児や若年者では回復に時間がかかることもあります。
ラグビーやサッカーなどのスポーツにて脳震盪を生じた場合には、安静を保ちつつ脳震盪を疑った時のツール5(CRT5)に則って評価を行い、医療機関を受診するようにしましょう。
急性硬膜外血腫
頭蓋骨に線状骨折(線状のひびが入った骨折)が生じると、頭蓋骨の内側を通る中硬膜動脈という血管が損傷し、出血を引き起こすことがあります。この出血によって、脳と頭蓋骨の間に血腫(血の塊)が形成される状態を硬膜外血腫と呼びます。
主な症状には、激しい頭痛と吐き気に続いて、嘔吐、意識障害の出現があります。
急速に進行する頭の中の出血により、血腫の厚さが1~2cm以上になる場合は、脳を圧迫して死に至るリスクが高いため、緊急手術による治療が必要となります。
急性硬膜下血腫
急性硬膜下血腫は、脳の表面にある血管が損傷し、脳を覆う硬膜と脳の間に血腫(血の塊)が形成される状態です。硬膜外血腫と異なり、脳全体で発生する可能性があり、特に前頭部・側頭部・頭頂部に多く発生します。
主な症状には、激しい頭痛や意識障害、片側の麻痺(半身の動きが鈍くなる)などの神経障害があります。
血腫の厚さが1cm以上になる場合、脳への圧迫が強まり、開頭血腫除去術という緊急手術 が必要になります。
硬膜外血腫に比べ、急性硬膜下血腫は脳損傷を伴うことも多くて予後が悪いとされています。緊急手術を行っても死亡率は55%に達するとも報告されています。しかし、早期診断を行い、受傷後4時間以内に開頭手術を実施することで、死亡率を低下させる可能性があるため、迅速な対応が極めて重要です。
脳挫傷
脳挫傷(のうざしょう)とは、強い衝撃により脳そのもの(脳実質)が損傷を受ける状態を指します。損傷した脳には脳出血や脳浮腫(脳の腫れ)が生じることがあり、症状の進行によっては重篤な影響を及ぼす可能性があります。
また、脳挫傷は外力が加わった部位とは反対側に発生することがあるのも特徴です。例えば、後頭部を強く打った場合でも、衝撃の反動により前頭葉に損傷(脳挫傷)が起こることがあります。この現象を対側損傷と呼びます。
スポーツによる頭部外傷
 スポーツ中の頭部外傷は、回転加速の外力が加わることが多く、重症化するリスクが高い とされています。特に注意が必要なのが脳振盪です。
スポーツ中の頭部外傷は、回転加速の外力が加わることが多く、重症化するリスクが高い とされています。特に注意が必要なのが脳振盪です。
脳振盪は、画像診断上において脳に明らかな損傷(器質的異常)がない状態を指しますが、スポーツ中に頭を打った後に脳振盪の症状が現れた場合、微細な脳損傷や脳出血、急性硬膜下血腫、脳挫傷を伴っている可能性があります。そのため、MRI検査で脳の状態を確認することがあります。
また、セカンドインパクト症候群という危険な状態にも注意が必要です。これは、1回目の頭部外傷後、数日から数週間のうちに2回目の外傷を受けることで、重篤な脳の腫れ(脳腫脹)が発生するものです。ボクシング、空手、柔道、ラグビーなどのコンタクトスポーツで多く見られ、特に18歳以下の若年者や、十分な休養を取らずに競技復帰した場合に発症しやすいとされています。
脳振盪が疑われる場合の対応
- 競技を直ちに中止し、安静を保ちつつ脳震盪認識ツール5(CRT5)に則って評価する。緊急性が認められた場合には救急要請をする。
- 緊急性のない場合でも十分な休養をとり、たとえ症状が消失しても医師や専門家による評価を受けるまでは競技に復帰してはいけない。
- 受傷後の1-2時間は一人で過ごさず、安静を心がけて過ごす。
- 競技への復帰には段階的な競技復帰へのプロトコル(GRTP)に従って行動する。
頭部外傷は軽度に見えても、後から症状が現れることがあります。適切な対応を行い、安全にスポーツを続けましょう。
高齢者の頭部外傷
 加齢に伴って身体(特に脚)の筋力の低下や歩行速度の減少、反射神経の低下、活動量の減少が進むことで、ちょっとした段差や平坦な場所でもつまづいて転倒し、打撲や骨折を引き起こすケースが少なくありません。
加齢に伴って身体(特に脚)の筋力の低下や歩行速度の減少、反射神経の低下、活動量の減少が進むことで、ちょっとした段差や平坦な場所でもつまづいて転倒し、打撲や骨折を引き起こすケースが少なくありません。
高齢者の頭部外傷の主な原因は転倒や転落で、特に年齢が高くなるにつれて歩行者が自動車と衝突する事故のリスクも上昇します。また、高齢者の中には抗血小板薬や抗凝固薬(血液をサラサラにする薬)を服用している人もおり、打撲による体内での出血が止まりにくくて重症化する可能性があります。
高齢者の
頭部外傷と慢性硬膜下血腫
高齢者の頭部外傷では、頭をぶつけた直後に異常がなくても、時間が経ってから症状が現れることがあります。特に注意が必要なのが慢性硬膜下血腫です。これは、頭部外傷後1~3ヶ月かけて脳と頭蓋骨の間に少しずつ血液が溜まり血腫を形成する病気です。
慢性硬膜下血腫が進行して血腫が大きくなってくると、以下のような症状が現れることがあります。
- 字が下手になった
- 箸が使いづらい
- お茶碗をひっくり返す
- 歩行が不安定になり、よく転ぶ
血腫が小さい場合は、内服薬での治療にて徐々に吸収されることもありますが、血腫が増大して脳を圧迫すると上記のような神経症状が出現してくるために、脳外科手術による血腫の除去が必要になります。脳外科手術を行うことで症状の改善と病気の治癒が期待できます。
周囲の方の気づきが大切
軽い打撲であっても、そのあとに慢性硬膜下血腫が発症する可能性があります。そのため、症状の経過をしっかり観察することが重要です。特に、高齢者や認知症の人は自身の症状をうまく伝えられないことがあります。そのため、ご家族や介護者が手足の動きが鈍くなったとか元気がない、普段と様子が違うなどの変化に気づくことが早期発見につながります。
高齢者が頭を打った場合は軽い打撲であっても慎重に経過を観察して、もしも異変を感じた場合には速やかに医療機関を受診することをおすすめします。
労災で受診される方へ
労災保険とは、仕事中や通勤途中で発生した怪我や病気に対して保険給付を受けられる制度です。正社員だけでなく、パートやアルバイトを含むすべての従業員が対象となります。
労災保険の申請には、勤務先の労災担当者が必要書類を準備する必要があります。なお、労災事故による治療は原則として健康保険の適用外となります。
必要な書類について
労災で受診される場合には、事前に下記の書類をご用意ください。
なお、書類をお持ちでない場合は、一旦自費診療にて受診していただくことになりますので、ご了承ください。
当院が1つ目の医療機関の場合
| 怪我や病気の 発生時 |
必要な書類 |
|---|---|
| 就業中 | 様式第5号 |
| 通勤途中 | 様式第16号の3 |
当院が2つ目以降の医療機関の場合
| 怪我や病気の 発生時 |
必要な書類 |
|---|---|
| 就業中 | 様式第6号 |
| 通勤途中 | 様式第16号の4 |
第三者行為について
第三者行為とは、自転車同士の事故やケンカなど他人の行為によって負った怪我を指します。
健康保険を利用して受診することも可能ですが、事前に保険組合の許可を得る必要があります。保険組合の確認が取れない場合は自費診療となります。